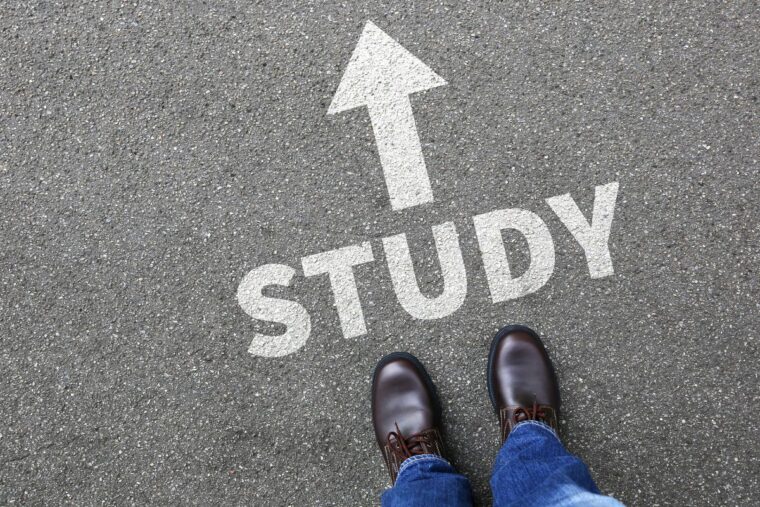宅建試験の合格を目指したいけど、「忙しくて勉強時間が取れない」「どこから手をつけていいかわからない」と悩んでいる方は多いはずです。
実は、しっかり計画を立てて効率的に勉強すれば、3ヶ月でも合格は十分可能です。
本記事では、最短で宅建合格を掴むための具体的な8つの勉強ステップを徹底解説。
無駄なくポイントを押さえ、短期間で合格レベルの実力を身につける方法をお伝えします。
これから宅建試験に挑戦する方は必見です!
宅建に3ヶ月で最短合格するためのおすすめ勉強法【8つのステップでOK】

先に結論からお伝えすると、宅建に3ヶ月で最短合格するための勉強法は次のステップになります。
- 宅建に合格したい理由の明確化
- 宅建試験について理解する
- 分野別の目標点数を設定
- 自分にあった教材を選ぶ
- テキストを読み込む
- 過去問を解いてみる
- 予想問題集を解いてみる
- 間違えた問題の解説を読んで復習する
これらを1つずつ説明していきます。
1.宅建に合格したい理由の明確化

最初にやるべきことは、「なぜ宅建試験に合格したいのか」を明確にすることです。
勉強を始めたばかりの頃はモチベーションが高くても、1ヶ月、2ヶ月と時間が経つにつれてやる気が低下しやすいからです。
実際、多くの人が仕事やプライベートの忙しさで途中で挫折した経験があるでしょう。
しかし、合格への強い動機や目標があれば、困難に直面しても踏みとどまりやすく、継続して努力しやすくなります。
だからこそ、最初に「なぜ宅建に合格したいのか」をはっきりさせることが重要です。
なぜ合格したいのか紙に書いてみるのがオススメです
目的を視覚化することで、意識が大きく高まり継続しやすくなります。
そのため、「なぜ宅建に合格したいのか」を具体的に紙に書き出すことを強くおすすめします。
「ただの精神論では?」と思うかもしれませんが、実際には勉強方法以上に重要なポイントです。
自分の合格への理由を明確にすることで、モチベーションが維持しやすくなり、つらい時期も乗り越えやすくなります。
まずは、宅建合格という目標に向けて、あなたの目的をしっかり言語化してみましょう。
2.宅建試験について理解する

次に大事なのは、宅建試験についてしっかり知ることです。
試験に合格するためには、まず試験の内容や仕組みを理解することがポイントです。
たとえば、合格率や試験科目、試験の日程などはちゃんと把握できていますか?
どんなに勉強しても、試験の申し込みを忘れてしまうと意味がありませんよね。
まだ詳しく知らない方は、宅建試験についてわかりやすくまとめた以下の記事を先に読んでから、またこちらに戻ってきてくださいね。

3.分野別の目標点数を設定

3つ目にすることが分野別の目標点数を設定です。
宅建試験には大きく分けて以下の4つの分野が出題されます。
- 宅建業法
- 権利関係
- 法令上の制限
- 税その他
では分野別にどのくらいの得点を取ればいいのでしょうか?
この分野別の目標得点をしっかりと把握しておくことで、その分野にどのくらいの比率で時間を使えばいいのかが分かってきます。
※以下は実際に私が目標としていた分野別の得点になるので参考にしてみてください。
宅建業法
目標得点:18点/20点
宅建業法は宅建試験で最も得点しやすい分野です。
内容も難しくないため、暗記すれば安定して点が取れます。
確かにひっかけ問題もありますが、基本を押さえれば見抜けるようになるので、問題を繰り返し解くことが大切です。
宅建業法は合否を左右する重要ポイントで、ここで満点近く取れれば合格の可能性が大きく高まります。
権利関係
目標得点:10点/14点
宅建試験で最も難しい分野が権利関係です。民法や借地借家法など幅広い法律知識が求められ、対策が難しいのが特徴です。
そのため、目標点は14点中10点を目指し、最低でも8点は確保したいところです。
権利関係に時間をかけすぎるより、宅建業法や法令上の制限など暗記科目に重点を置く勉強法をおすすめします。
法令上の制限
目標得点:6点/8点
法令上の制限は宅建業法と同じく暗記が中心ですが、「国土利用計画法」や「農地法」、「建築基準法」など覚える内容が非常に多い分野です。
そのため苦手意識を持つ方も多いでしょう。
私自身も最初は苦労しましたが、繰り返し学習するうちに全体像がつかめ、得点が伸びていきました。
最初は難しく感じても、慣れれば宅建業法と同様に得点源となる分野です。
税その他
目標得点:6点/8点
「税金」や「住宅金融支援機構・景品表示法・統計」など一見すると幅広い分野に感じますが、宅建試験で出題されるポイントはほぼ決まっています。
そのため、実は得点しやすい分野といえます。
過去問を繰り返し解くことで、出題傾向やよく出る問題のパターンが見えてくるはずです。
効率よく得点を狙いたいなら、ここで確実に点を取りましょう。
合計点数は40点と厳しめに設定しておく
分野ごとの目標点数をしっかり取れれば、合計40点に届きます。
近年は宅建試験の合格点が上がる傾向にありますが、40点取れれば確実に合格ラインを超えます(過去に40点以上の年はありません)。
もちろん試験の難易度によって得点には差が出ますが、あくまで目標として40点を意識しておくことが重要です。
安定して合格を目指すには、各分野での得点計画を立てることが鍵になります。
4.自分にあった教材を選ぶ

4つ目のステップでは、これから使う宅建の学習教材を選びましょう。
中でも特におすすめなのが「通信講座」です。
通信講座は通学スクールより費用が抑えられ、独学よりも効率的に学べるカリキュラムが整っています。
私も市販テキストから通信講座に変えたことで、理解度が大きく向上し得点も伸びました。
どういった通信講座がおすすめなのかは別の記事にまとめているのでぜひそちらを参考にご自身にあった通信講座を選んでみてください。

5.テキストを読み込む

いよいよ宅建合格に向けた本格的な学習ステップに入ります。
まずは、通信講座に付属している基本テキストをしっかり読み込みましょう。
目安は最低3周、可能であれば5周以上です。
最初は内容が理解できず、読むのがつらく感じるかもしれませんが、まずは手を止めずに最後まで読み進めることが大切です。
不思議と、何度も読み返すうちに少しずつ内容が頭に入ってくるようになります。
この「テキスト読み込み」は学習初期の大きな壁ですが、ここを越えることでその後の理解がスムーズになります。
6.過去問を解いてみる

テキストを最低3周以上読み込めたら、次は宅建の過去問演習に進みましょう。
3周ほどテキストを読んでいれば、基礎知識はある程度身についているはずです。
ここからはアウトプット中心の学習に切り替えます。
最初は解けなくても問題ありません。
何度も問題を解いていく中で、宅建試験の出題傾向や重要ポイントがつかめてくるはずです。
過去問は何年分解けば良いのか?
宅建の過去問は10年分を2周以上解くのが理想です。
時間が厳しい場合は、直近5年分でも十分効果があります。
過去問を繰り返し解くことで、よく出る出題パターンや頻出テーマが自然と見えてきます。
目標は、過去問で8割以上の正答率をキープできる状態を作ることです。
通信講座を利用している方は、付属の過去問集を活用しましょう。
解説が丁寧なので、間違えた問題は必ず解説を読んで理解を深めてください。
7.予想問題集を解いてみる

宅建の過去問を10年分×2周ほど解き終えたら、次は予想問題集や模擬試験に取り組みましょう。
過去問ばかりを繰り返していると、問題に慣れて答えを覚えてしまうため、実力が正しく測れなくなります。
その段階に来たら、市販の予想問題集や模試を活用して、初見の問題にどんどん挑戦していくのが効果的です。
宅建試験本番に向けて、応用力と対応力を鍛える大切なステップになります。
※通信講座なら過去問とは別に問題集がついているのでそれを解いていけばOKです。
8.間違えた問題の解説を読んで復習する

このステップは宅建合格のために非常に重要です。
問題を解いた後は、間違えた問題の解説を必ず読んで丁寧に復習しましょう。
「とにかくたくさん問題を解けばOK」と考える人もいますが、それだけでは効率が悪く、学習効果が下がります。
例えるなら、何も考えずに素振りだけを繰り返している野球選手のようなものです。
「なぜ間違えたのか?」「どこが理解できていないのか?」を見直すことで、確実に実力が身についていきます。
問題→解説→テキストを繰り返す
宅建試験の学習では、問題を解いたあとに解説を確認し、さらにテキストに戻って知識を整理することが大切です。
この「問題→解説→テキスト」の3ステップを繰り返すことで、苦手分野が少しずつ減っていきます。
特に、間違えた問題をテキストで再確認することで、理解度が一気に深まり、学習効果も大幅にアップします。
私は間違えた問題をノートにまとめていましたが、直前期に苦手なポイントだけ見直せるので非常に効率的でした。
1〜8のステップをとにかく繰り返せば本番で40点以上狙える

ここまで紹介してきた宅建合格までの8つのステップを実践すれば、本番で40点以上を狙うことは十分可能です。
特にステップ5〜8は、時間が許す限り何度も繰り返すことがポイントです。
繰り返し学習することで苦手分野が減り、試験直前には「やるべきことはすべてやった」と自信を持って本番に臨めるはずです。
宅建に3ヶ月で合格するために必要な勉強時間は?

宅建合格には一般的に300〜500時間の勉強時間が必要と言われています。
もちろん個人差はありますが、多くの合格者は平均して約300時間勉強しています。
- 1日1時間毎日勉強したとすると300日
- 毎日2時間ずつであれば150日
- 毎日3時間ずつであれば100日
3ヶ月で一発合格を目指すなら、毎日約3時間の勉強が目安です。
しかし、社会人にとって毎日3時間の確保は難しいため、時間にこだわりすぎず質の高い学習を心がけましょう。
ただ漫然と3時間学習するより、工夫しながら2時間集中して勉強する方が効果的です。
また、独学と通信講座では必要な勉強時間にも違いが出るため、自分に合った方法を選ぶことが大切です。
どの通信講座がおすすめかは下の記事で紹介しているので、最適な通信講座を選んでガッツリと勉強時間を短縮化させてください。