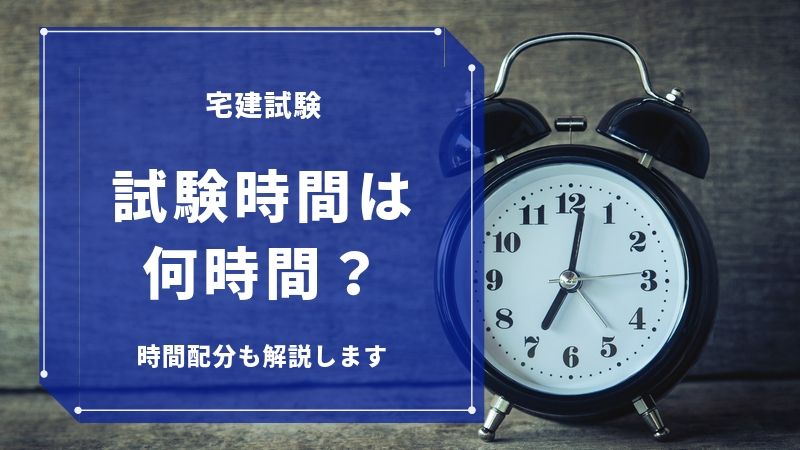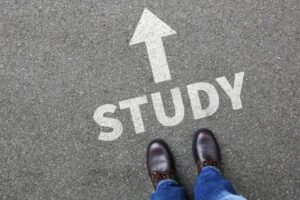宅建試験は50問・2時間と決まっていますが、実際に受けると「時間が足りなかった…」という声がとても多いです。
どれだけ知識があっても、時間配分を間違えると得点を取りこぼしてしまいます。
特に、どの問題から解くか・どのくらい時間をかけるかは、合否を左右する重要なポイントです。
この記事では、宅建試験の試験時間と各パートの理想的な時間配分、さらに「時間切れを防ぐ解答順の戦略」まで具体的に解説します。
試験本番で焦らず、実力を出し切るためのヒントをぜひ参考にしてください!
宅建の試験時間は何時間?

宅建試験の所要時間は13時〜15時までの「2時間(120分)」です。
出題数は全50問で、マークシート方式となっています。
この50問を120分で解くということは、単純計算で1問あたり約2分半のペースです。
ですが、問題の難易度や分野ごとの特徴により、すべてを均等に解くのは現実的ではありません。
特に初受験者は、じっくり考えすぎて見直しの時間が足りなくなる傾向があります。
宅建試験の出題範囲は以下の4つの分野に分かれています。
- 権利関係(14問)
- 宅建業法(20問)
- 法令上の制限(8問)
- 税・その他(8問)
各分野での問題数が異なるため、時間配分の調整が重要になります。
5問免除を受ける人は試験時間が異なるので注意
登録講習を修了した人は「5問免除」の制度を利用できます。
この制度を受けると、宅建試験の出題数と試験時間が短縮されます。
通常の受験者は13時〜15時までの「50問・2時間(120分)」ですが、5問免除の人は13時10分〜15時までの「45問・1時間50分(110分)」です。
つまり、試験時間が10分短くなるので注意が必要です。
5問免除でカットされるのは「税・その他」の分野のうち、講習でカバーされる5問です。
実際に解く必要があるのは、以下の45問です。
- 権利関係(14問)
- 宅建業法(20問)
- 法令上の制限(8問)
- 税・その他(3問)
特に、宅建業法や法令上の制限はスピーディーに解けるように練習しておきましょう。
宅建試験当日の時間配分・順番

次に試験当日の時間配分を詳しく紹介します。
以下のように時間を使うと最後の見直しまで余裕を持って出来るのでおすすめです。
- 13:00-13:30 宅建業法
- 13:30-13:50 法令上の制限
- 13:50-14:05 税・その他
- 14:05-14:35 権利関係
- 14:35-15:00 最終の見直し
時間配分について深掘りしていきます。
13:00-13:30の時間配分 宅建業法
まずは一番簡単な分野と言われている宅建業法から解いていきましょう。
宅建業法は、覚えるべきポイントをおさえれば満点も狙える重要科目です。
数字・用語・引っかけ問題への対策を徹底し、安定して得点できるようにしておきましょう。
得点源である宅建業法を確実に攻略することが、宅建試験合格への近道です。
13:30-13:50の時間配分 法令上の制限
次に法令上の制限を20分間で解いていきましょう。
法令上の制限は、出題数こそ多くないものの、得点源として差がつきやすい分野です。
数字の暗記+計算問題への対策をバランスよく行い、引っかけ問題にも冷静に対応できるよう準備しましょう。
「難しそう」と感じる受験者が多い分、対策次第で一気に有利になります。
13:50-14:05の時間配分 税・その他
次に税・その他を15分間で解いていきましょう。
税・その他は出題範囲が広く、ややとっつきにくい分野です。
しかし、出題パターンはある程度決まっているため、ポイントを絞った学習で得点しやすくなります。
計算ミスを減らし、出やすい税金・統計・評価の問題を落とさないようにして、確実に得点しましょう。
14:05-14:35の時間配分 権利関係
権利関係は宅建試験で最も配点が大きく、合否を左右する重要分野です。
しかし問題が難しいため、試験序盤で解くと時間がかかり、焦りや集中力の低下を招きやすいです。
そこで、権利関係は試験の最後に回し、残り30分で解くのがおすすめです。
最初は飛ばして、終盤に余裕を持って解くことで効率よく得点できます。
権利関係の14問を最後に集中して解くことが、合格への大きなカギとなります。
14:35-15:00の時間配分 最終の見直し
最後の余った時間で問題の見直しをしていきましょう。
問題にも選んだ答えをマークしておくと、マークシートの塗りつぶしミスがないか簡単に見直すことが出来るのでおすすめです。
焦ってしまって違う答えを選んでいた、マークしていたで不合格になる人はたくさんいます。
それも実力なので、最後まで油断せずに徹底的に見直しをするようにしましょう。
学習段階から試験の時間配分を意識して問題を解こう

宅建試験では時間配分が合否を大きく左右します。
学習段階から試験時間を意識して問題を解く習慣をつけましょう。
本番で時間切れにならないためには、練習時から時間を計って解くことが重要です。
- 全体の問題数と配分時間を把握する
- 分野ごとに解く順番を決めて練習する
- 難しい問題は後回しにする戦略を身につける
時間を意識すると、問題の優先順位が自然と見えてきます。
例えば、権利関係のような長文問題は時間がかかりがちです。
学習時に「この問題は何分で解けるか」を確認しながら取り組むと効果的です。
また、時間配分の感覚をつかむと、試験本番でも冷静に対応できます。
学習段階での時間配分意識は合格への近道です。
宅建の試験時間が足りない…を防ぐために気をつけるべき3つのこと

宅建試験で時間切れを防ぐために、気をつけるべき3つのポイントを紹介します。
- 試験会場には開始1時間前に到着する
- 試験前には必ずトイレを済ませる
- 分からない問題は考え込まず飛ばす
この3つのポイントを押さえ、効率的な時間配分で宅建試験を乗り切りましょう。
試験会場には1時間前に到着しておくこと
宅建試験当日は余裕を持った行動が合格のカギです。
試験開始の1時間前には必ず試験会場に到着しましょう。
遅刻やトラブルで試験時間を失うリスクを避けられます。
また、早めに到着して軽く散歩することで、緊張を和らげて集中力を高める効果もあります。
試験前には必ずトイレに行っておく
宅建試験前には必ずトイレを済ませておくことが重要です。
試験中にトイレに行く場合、試験監督の許可が必要で、その間も試験時間は減ってしまいます。
試験開始前は問題なくても、途中で急にトイレに行きたくなることはよくあるため、事前の準備が合格のポイントです。
分からない問題は考え込まずにとにかく飛ばすこと
宅建試験では分からない問題に時間をかけすぎないことが重要です。
目安は1分間で解けなければ、すぐに次の問題へ進みましょう。
時間配分を守ることで、最後まで問題を解くチャンスを確保できます。
まずは全問題を一通り解くことを意識し、効率よく得点を積み重ねましょう。
試験当日は時計を持っていくことを忘れずに

試験時間を自分で管理することで、時間切れを防ぎやすくなります。
スマホの時計は使用禁止のことが多いため、腕時計が最適です。
- 電池切れのない時計を準備する
- 試験開始前に時間を合わせておく
- 視認性が良い時計を選ぶ
時計がないと時間配分が狂いやすく、焦ってミスを誘発するリスクがあります。
時間管理は宅建試験の合格に欠かせないポイントです。
試験実施団体は持ち込みの時計について次のような条件を提示しています。
アナログ時計がおすすめ
デジタル時計には時計以外の機能が含まれている可能性があるので、万が一のことを考えてアナログを用意しておく方が安心です。
時計は安いもので構わないので、当日までに用意しておきましょう。
試験時間を制する者が宅建を制す!時間配分の意識が合格のカギ

宅建試験の時間配分まとめ
- 13:00-13:30 宅建業法
- 13:30-13:50 法令上の制限
- 13:50-14:05 税・その他
- 14:05-14:35 権利関係
- 14:35-15:00 最終の見直し
宅建試験は50問を2時間で解く必要があり、時間の使い方が合否を左右します。
学習段階から時間を測って問題を解くクセをつけ、本番で焦らず対応できるよう準備しましょう。
限られた試験時間をどう使うかは、事前の意識と行動で大きく変わります。
確実に得点を積み上げるためにも、時間配分を制することが合格への最短ルートです。