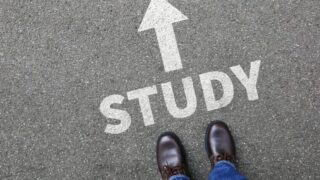宅建の法令上の制限おすすめの勉強法・覚え方を解説していきます。
- 法令上の制限おすすめの勉強法・覚え方
- 宅建の法令上の制限は何点取れれば良いのか?
- 法令上の制限を勉強するのにおすすめの教材
宅建の法令上の制限おすすめの勉強法・覚え方

結論、次の3つのステップが宅建の法令上の制限おすすめの勉強法・覚え方になります。
- 基本テキストを3周以上読み込む
- 過去問を解きつつ、出題傾向を把握する
- 市販模試で初めて見る問題にチャレンジしてみる
これらを1つずつ深掘りしていきます。
基本テキストを3周以上読み込む
基礎も分からない状態で先に進んでしまうと、すぐに挫折してしまいます。
初めは辛いと思いますが、読み進めていくにつれて理解が深まっていくのを感じることができます。とにかく先に進むという意識で3周以上は自分の選んだ基本テキスを読み込みましょう。
過去問を解きつつ、出題傾向を把握する
基本テキストを3周以上読み終えたら、次は過去問を解いていきましょう。
この段階で過去問を解くことによって次のようなメリットがあります。
- 基本テキストでインプットした知識をアウトプットすることで理解が深まる
- 法令上の制限でよく出題されている問題の傾向が分かる
過去問を使うことで覚えるべきポイントがより一層分かってくるはずです。その状態でもう一度基本テキストに立ち返って学習してみるとより効率的に重要なポイントを覚えれるようになるのでおすすめです。
過去問は直近10年分を最低でも2周はしておくのがベストです。
予想問題集で初めて見る問題にチャレンジしてみる
最後の仕上げとして市販模試を解いてみましょう。市販模試は各予備校が今年の試験で出題される問題を予想して作られた模試です。
過去問に慣れてくると問題を覚えてくるので、できた気になりがちです。ただ市販模試の初めて見る問題を解いてみると理解できてない箇所が浮き彫りになってくるはずです。
その浮き彫りになった箇所をもう一度基本テキストに立ち返って丁寧に復習していきましょう。
宅建の法令上の制限は何点取れれば良いのか?

法令上の制限は8点分出題されますが、6点は最低でも取っておきたいです。
もし法令上の制限で2点分しか取れなかったとすると他の宅建行法や権利関係で得点を落とすことができなくなってしまうことになります。
そうすると結果として合格できる確率を下げてしまうことになります。
ちなみの私が想定する各分野の目標得点は次のようになります。
- 宅建業法:16点/20点
- 権利関係:8点/14点
- 法令上の制限:6点/8点
- 税・その他:5点/8点
- 合計:35点/50点
合計点数は35点を目安にしていますが、最近では合格点数が37点の年も増えています。なのでできればこの目標点数+2点分をどこかの分野で得点を取りたいところですね。
法令上の制限は最低でも8点6点は取れるように頑張りましょう!
宅建法令上の制限でおすすめの教材

結論として宅建の法令上の制限を勉強するのにおすすめの教材は、通信講座のフォーサイトです。
フォーサイトのテキストはフルカラーテキストでとにかく分かりやすいと評判がとにかく良いです。
説明も分かりやすく苦手意識を持っている分野でもフォーサイトのテキストをしっかりとと読んでいけば理解ができてきます。
フォーサイトについてより詳しい解説は下の記事で紹介しているので宅建法令上の制限の得点をUPしたい方はそちらを参考にしてみてください。



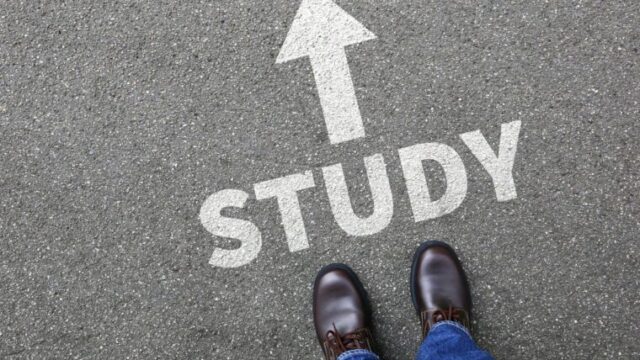





 フォーサイト
フォーサイト 
 アガルート
アガルート 
 スタディング
スタディング